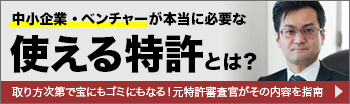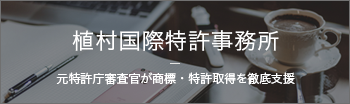測量業と建設業報告書作成 年1回(手控え)
 |
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
測量業と建設業 決算後の届出(毎年)
会社(法人)へ委任状を送る
↓
(前期の報告書も参照 OneDrive2-001 行書(新)4-000 建設業)
※手順詳細は、建設業見出し参考
https://www.mlit.go.jp/
建設業 決算変更届R〇.7.25第〇期
測量業
提出書類PDF
①測量法第55条の8第1項の規定に基づく書類 ※5年ごとに登録更新しているため、年度に注意。
②営業経歴書
③財務事項一覧表
④完成測量原価報告書
⑤決算報告書
⑥納税証明書
⑦営業所ごとの測量士・測量士補の人数 ※変更がない場合は省略可
⑧委任状
建設業
提出書類PDF
①表紙 変更届出書
②工事経歴書 (さく井・とび土工・土木工事)
③直近3年の各事業年度における工事施工金額
※④貸借対照表
※⑤損益計算書
※⑥完成工事原価報告書
※⑦株主資本等変動計算書
※⑧注記表
⑨事業報告書
⑩納税証明書その1
⑪使用人数 注:前期と変更ある場合
⑫健康保険等の加入状況 注:前期と変更ある場合
⑬委任状
※なんでも経審で作成
参考様式をダウンロードし、昨年度を参考に入力する。→そしてPDFに
【工事経歴書】
請負工事の一覧のうち金額の大きい上位10件を記入→小計
合計金額→請負工事全部の合計額=損益計算表の完成工事高
※千葉県(TheHuman分)は上位13件記載
合計金額は、損益計算書の工事売上高に合わせて金額修正。
【直近3年の工事施工金額】
合計金額は、損益計算書の工事売上高に合わせて金額修正。
事業年度の考え方
事業年度:2月1日~翌年1月31日
許可申請日(届出日):令和5年3月3日の場合。
直前の決算期は「令和5年1月31日」です。ここから起算した過去3年間の事業年度を記入します。
10期(令和2年2月1日~令和3年1月31日)
11期(令和3年2月1日~令和4年1月31日)
12期(令和4年2月1日~令和5年1月31日)
「なんでも経審」で 財務諸表などが作成できる。
各種申請書類→すでに建設会社の登録済みの場合は、新規で第〇期を追加し、入力。
財務諸表表紙・①貸借対照表・②損益計算書・③完成工事原価報告書・④株主資本等変動計算書・⑤注記表(財務諸表5表)、そして
(兼業事業売上原価報告書・付属明細書・換算報告書)をPDF作成できる。
昨年度がある場合は、前期データを反映させ、前期の決算書もPDFで開きながら作業する。
【財務諸表】
決算書と、昨年度の財務諸表を見ながら入力
※財務諸表=貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書
完成工事原価報告書:経費欄 当期経費合計から外注加工費を引く
:完成工事原価 Ⅰ~Ⅳの合計を記載する
損益計算表
兼業事業売上原価=期首棚卸高から期末棚卸高を引く
損益計算書入力チェック→OKで、財務諸表作成状況→NGは、詳細項目の数字にミスがあることが多い
販売費および一般管理の計算内訳は、決算書の順番で入力をしていくと、足りない項目がわかりやすい
【株主資本等変動計算書】
基本の項目は
列側:資本金、繰越利益余剰金、利益余剰金合計、株主資本合計、純資産合計
行側:当期首残高、当期純利益、登記未残高
減価償却累計額
未入力→合計額の欄との混同に注意
【注記表】
金額を今年度の決算書・個別注記表を参照し入力
文言は決算変更届の前期・注記表を参照 ※文言は個別注記表ではない。
雇用契約に係る重要事項事前説明書は、全員分
コメント部分ではないかも。
【事業報告書】
経常利益/損失→損益計算書の当期純利益/損失
完成工事高→損益計算書の完成工事高
【健康保険等の加入状況 注:前期と変更ある場合】
従業員数に社長も入る(カッコ内に1人)と入力
雇用保険欄は、雇用保険適用事業所設置届の「事業書番号」を入力
「労働保険番号」ではない。
【納税証明書と委任状】
都道府県知事許可 法人の場合 法人事業税(都道府県税事務所(支所)で発行)
都道府県知事許可 個人の場合 個人事業税(都道府県税事務所(支所)で発行)
国土交通大臣許可 法人の場合 法人税(税務署で発行)
国土交通大臣許可 個人の場合 所得税(税務署で発行)
なんでも経審を使用しない場合は用紙をダウンロード
以下補足
- 左側「資産の部」:集めた資金を運用している方法を示す
- 右側「負債の部」と「純資産の部」:会社が事業に必要な資金を集めた方法を示す
→→「資産」は資産をどのように運用したか、が分かる欄。資産額ではない!!
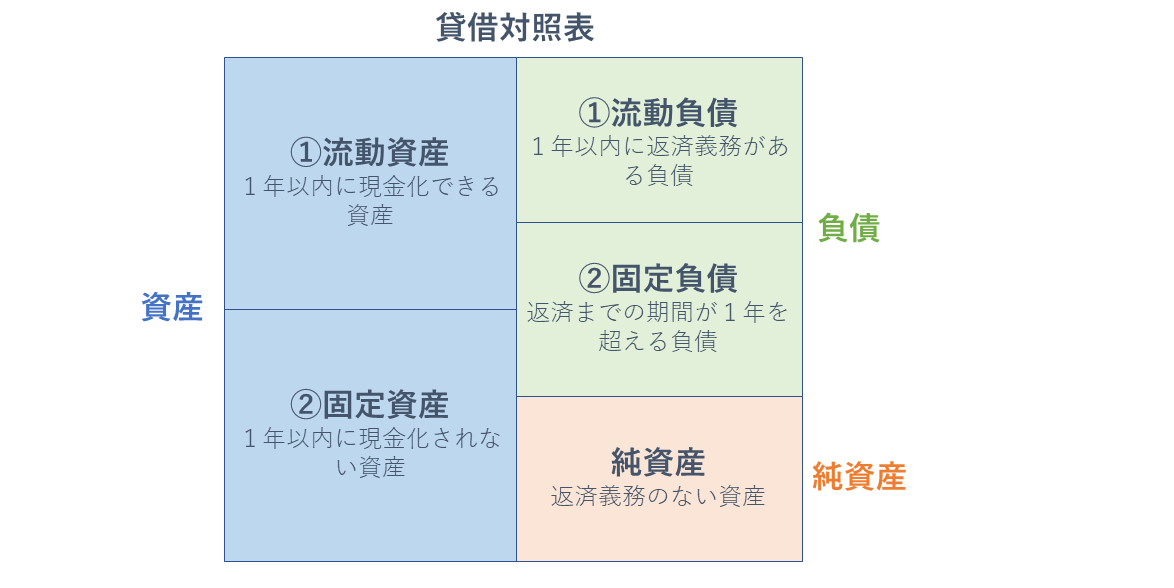
要点:決算書を建設業用に「翻訳」したものが建設業財務表である。
(書類の入力の際、数字のチェックに使える)
勘定科目は決算報告書と異なり、建設業特有の勘定科目を使用します。
勘定科目の違いを想定して、作成する必要があります。
貸借対照表
- 完成工事未収金 ← 売掛金
- 未成工事支出金 ← 仕掛品
- 工事未払金 ← 買掛金、未払金
- 未成工事受入金 ← 前受金
損益計算書
- 完成工事高 ← 売上高
- 完成工事原価 ← 売上原価
- 完成工事総利益 ← 売上総利益
【書類の税抜・税込みについて】
免税事業者(消費税の免除をされる小規模事業主・個人事業主)は、税込み処理。課税事業者で、経審(公共事業を発注者から直接請け負う建設業者が受ける審査)を受ける予定がない場合、税込み・税抜きどちらの処理でもOK。
ただ、すべての書類をどちらかに揃える必要がある。
参考情報
書面で請求する場合
納税証明書を書面で請求する場合の手数料は下表のとおりです。
| 納税証明書の種類 | 手数料 |
|---|---|
| 納税証明書(その1)(その2) | 税目数 × 年度数 × 枚数 × 400円 |
| 納税証明書(その3)(その4) ※(その3の2)(その3の3)も含む |
枚数 × 400円 |
なお、手数料を収入印紙で支払う場合、収入印紙に消印すると無効となってしまいます。また、郵送での受取を希望する場合は、郵送料(切手)や返信用封筒の準備も忘れないようにしましょう。
決算書の依頼・受領
標準報酬決定書を取得して、人数を確認でもよい